|
1号線(東山線) 6両組成×23編成=138両(最大在籍数) 配置:藤が丘工場
5100-5200-5300-5400-5500-5600
電気:第3軌条600V 軌間:1435mm(標準軌) 車長:15m(小型)
 引退車両「東山線5000形」コンテンツ 引退車両「東山線5000形」コンテンツ |
 |
 車 両 概 要 車 両 概 要 |
 |
東山線5000形車両は,昭和55年から平成27年までの35年間,名古屋の東西大動脈輸送に活躍した車両です.
【5000形誕生の経緯】
名古屋市初の地下鉄として昭和32年に開業した地下鉄東山線は,開業当初は2両組成でした.
それ以降,東山線は名古屋の大動脈として急速に成長し,順次1両ずつ増結してゆき,現在では6両組成の,また運転間隔もラッシュ時約2分間隔という超過密路線に成長しました.
この結果,駅やトンネル内部の温度上昇が著しく,それまで非冷房車両のみで運行されていた地下鉄の冷房化が望まれましたが,トンネル断面を小さくするため採用された小型車両がゆえ,車体床面も低く,車体屋根とトンネル天井との余裕もないなど,問題が山積みでした.
昭和55年(1980年),電子技術は進歩し,静止インバータの採用などにより薄形冷房装置の屋根上設置が可能となり,東山線初の冷房車として5000形の量産先行試作車1編成が登場しました.
冷房化以外にも,黄電時代からの交通局車両設計基本方針3S(安全Safety,迅速Speedy,静粛Silent)を受け継ぐ一方,省エネルギー,メンテナンスフリーに重点が置かれています.
その後昭和57年(1982年)から平成2年(1990年)にかけて23編成138両が量産・増備され,それまでの古い"黄電"を置き換えました.
アルミ車体の近代的な外見ながら,市電時代から続く技術や,他都市の地下鉄では見受けられない"黄電仕様"など,新旧混在した独特の雰囲気がこの車両の特徴です.
【5000形の終焉】
その後増備された5050形と合わせ計50編成で運用されていた東山線ですが,予備編成の見直しに伴う減車措置がとられ,平成16年(2004年)3月27日に打子式ATSからATCに保安装置が切り替えられた際に,5101編成と5102編成にATC車上装置が取り付けられることなく,除籍・廃車となりました.
さらに晩年は機器劣化や走行時の横揺れが激しくなるなど老朽化が進んでいること,平成27年度のホーム柵導入に対応するための機器を新規搭載するスペースが無いことから廃車が決定.
平成20年(2008年)3月から後継車両N1000形の運転が始まり,続々と運用を離脱.平成27年(2015年)8月28日をもって定期運用から離脱し,8月30日のラストランイベントをもって全車引退しました.
引退後の車両は,5編成が海外輸出されました.
国内に残った18編成は順次解体され,令和4年(2022年)6月27日の解体搬出を最後に消滅しました.
 5000形 編成表 5000形 編成表 |
 |
5000形は,昭和55年(1980年)から平成2年(1990年)にかけて,23編成138両が増備されました.
廃車は平成16年(2004年)から平成27年(2015年)にかけて行われています.
表中の廃車時期とは,運用を離脱した年月のことで,解体処分された年月ではありません.
車体艤装は日本車両と日立製作所が担当しています.
主電動機とチョッパ制御装置は日立製作所と三菱電機が製造しています.
| 次 |
導入 |
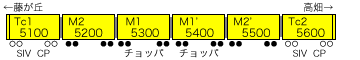 |
車体
艤装 |
主電動
機・
制御 |
廃車時期 |
| 1次車 |
S55年 |
5101 − 5201 − 5301 − 5401 − 5501 − 5601 |
日車 |
※ |
H16年 3月 |
| 2次車 |
S57年 |
5102 − 5202 − 5302 − 5402 − 5502 − 5602 |
日車 |
三菱 |
H16年 4月 |
| 5103 − 5203 − 5303 − 5403 − 5503 − 5603 |
日車 |
三菱 |
H25年 7月 |
| 5104 − 5204 − 5304 − 5404 − 5504 − 5604 |
日車 |
三菱 |
H24年 8月 |
| 5105 − 5205 − 5305 − 5405 − 5505 − 5605 |
日車 |
三菱 |
H21年12月 |
| 5106 − 5206 − 5306 − 5406 − 5506 − 5606 |
日車 |
三菱 |
H20年 3月 |
| 5107 − 5207 − 5307 − 5407 − 5507 − 5607 |
日車 |
日立 |
H22年10月 |
| 5108 − 5208 − 5308 − 5408 − 5508 − 5608 |
日車 |
日立 |
H26年6月 |
| 5109 − 5209 − 5309 − 5409 − 5509 − 5609 |
日立 |
日立 |
H27年2月 |
| 5110 − 5210 − 5310 − 5410 − 5510 − 5610 |
日立 |
日立 |
H21年 3月 |
| 5111 − 5211 − 5311 − 5411 − 5511 − 5611 |
日立 |
日立 |
H24年 9月 |
| 3次車 |
S58年 |
5112 − 5212 − 5312 − 5412 − 5512 − 5612 |
日車 |
日立 |
H24年11月 |
| 4次車 |
S59年 |
5113 − 5213 − 5313 − 5413 − 5513 − 5613 |
日車 |
三菱 |
H26年7月 |
| 5114 − 5214 − 5314 − 5414 − 5514 − 5614 |
日立 |
日立 |
H27年8月 |
| 5次車 |
S60年 |
5115 − 5215 − 5315 − 5415 − 5515 − 5615 |
日車 |
三菱 |
H24年12月 |
| 5116 − 5216 − 5316 − 5416 − 5516 − 5616 |
日立 |
日立 |
H26年7月 |
| 6次車 |
S61年 |
5117 − 5217 − 5317 − 5417 − 5517 − 5617 |
日車 |
三菱 |
H24年 8月 |
| 5118 − 5218 − 5318 − 5418 − 5518 − 5618 |
日立 |
日立 |
H25年10月 |
| 7次車 |
S62年 |
5119 − 5219 − 5319 − 5419 − 5519 − 5619 |
日車 |
三菱 |
H25年10月 |
| 5120 − 5220 − 5320 − 5420 − 5520 − 5620 |
日車 |
日立 |
H27年4月 |
| 8次車 |
S63年 |
5121 − 5221 − 5321 − 5421 − 5521 − 5621 |
日車 |
三菱 |
H25年 5月 |
| 5122 − 5222 − 5322 − 5422 − 5522 − 5622 |
日立 |
日立 |
H25年 6月 |
| 9次車 |
H2年 |
5123 − 5223 − 5323 − 5423 − 5523 − 5623 |
日車 |
三菱 |
H27年 3月 |
※1次車(S55年製)5101編成の主電動機・制御器は2メーカーが製造を担当しています.
(5201,5301号車は三菱/5401,5501号車は日立)
 主 要 諸 元 表 主 要 諸 元 表 |
 |
車体全長は鶴舞線20mに対して東山線15.6m,幅も鶴舞線2.75mに対して東山線2.5mと,小形車両となっています.
4M2Tの6両固定編成で,3両1ユニットとして機器を分散配置しています.
AVFチョッパ制御で,車輪は市電時代から続く弾性車輪を採用しています.
 |
| ←藤が丘 |
高畑→ |
|
| 形 式 |
5100形 |
5200形 |
5300形 |
5400形 |
5500形 |
5600形 |
| 車 種 |
Tc1制御車 |
M2電動車 |
M1電動車 |
M1'電動車 |
M2'電動車 |
Tc2制御車 |
| 自重 |
22.0t |
24.2t |
24.2t |
24.2t |
24.2t |
22.0t |
| 定員(座席) |
110人(38席) |
115人(44席) |
110人(38席) |
| 車体寸法 |
長さ15,580mm× 幅2,508mm(2,546mm)× 高さ3,440mm |
| 床面高さ |
960mm |
| 出 入 口 |
幅1,300mm× 高さ1,850mm 片側3カ所/両 |
| 台 車 |
ペデスタル式空気バネ台車 固定軸距1,800mm |
| 台車形式 |
TN-10T |
TN-10M |
TN-10M |
TN-10M |
TN-10M |
TN-10T |
| 車 輪 |
剪断形(SAB)弾性車輪 φ763mm |
| 基礎ブレーキ |
油圧式ディスクブレーキ |
| 駆動装置 |
WN平行軸カルダン駆動(5200〜5500) |
| 主電動機 |
直流直巻電動機 95kW×4(5200〜5500) |
| 制御装置 |
自動可変界磁式(AVF)チョッパ制御 回生ブレーキ付(5300,5400) |
| ブレーキ装置 |
MBS-R 電気指令式電空併用ブレーキ |
| 補助電源装置 |
直接12相接続三相インバータ75kVA(5100,5600) |
| 冷房装置 |
天井集約分散形(12,500Kcal/h × 2台/両) |
| 列車無線装置 |
誘導無線式 |
| 信号保安装置 |
(登場時)打子式ATS →(現在)車内信号式ATC |
▼もどる |
