|
高速度鉄道6号線(桜通線) 5両組成×20編成=100両在籍 配置:日進工場
編成:6100-6200-6300-6700-6800
電気:架空線式DC1500V 軌間:1067mm(狭軌) 車長:20m(大型)
 桜通線 6000形 コンテンツ 桜通線 6000形 コンテンツ |
 |
準備中.
 車 両 概 要 車 両 概 要 |
 |
桜通線6000形車両は,昭和62年(1987年)に交通局初のVVVFインバータ制御車として登場しました.
【6000形誕生の経緯】
桜通線6000形車両は,開業に先立つ昭和62年に試作編成(一次車:6101H)が登場しました.
しばらくは鶴舞線で試運転と営業運転が行われ,性能が確認された後,平成元年(1989年)に12編成を量産し(二次車),桜通線開業時には試作編成の改造と合わせ4両組成13編成で営業運転を開始しました.
平成6年(1994年)の今池〜野並間の延伸開業時には中間車を新造し5両組成としました.また,新たに7編成を増備し(三次車),桜通線は5両組成20編成100両の陣容となりました.
平成23年(2011年)の野並〜徳重間延伸開業時には新型車両6050形が登場しましたが,輸送力増強用の4編成のみの増備に留まっています.
20編成を擁する6000形車両は,これからも当面の間は,桜通線の主役であることには変わりありません.
【6000形の特徴】
地下鉄桜通線は,将来構想で名鉄線との相互直通が予定されており,さらに列車の大規模検査は,連絡線を経由して鶴舞線の日進工場にて行われるため,狭軌で架空線式の鶴舞線と同規格で車両設計がされています.
現在では主流となったVVVF制御装置のほか,軽量オールステンレス車体,ボルスタレス台車,LED式車内案内表示装置,運転台モニターなどは6000形が初採用であり,以後平成19年のN1000形登場までは交通局の標準車両となるなど,その功績は大きいと言えます.
その他桜通線の特徴として,平成5年よりATOによる自動運転を行うとともに,運転士のみ乗務するワンマン運転を行っていることが挙げられます.このため桜通線のホームは全て島式で,運転士が安全確認しやすいよう,運転台が通常とは逆の右側に設置されています.
【進化を続ける6000形】
6000形はこれまでに何度も改造工事を受けてきました.
平成5年からは中間車を新造して既存12編成の4両組成→5両組成化が行われました.
またATO機器搭載とワンマン運転対応工事が行われました.これにより平成6年2月よりATOによるワンマン運転を行っています.
平成20年からはホーム柵制御装置を搭載する可動式ホーム柵対応工事が行われました.これにより平成23年1月より可動式ホーム柵の運用を開始しています.また同時に運転状況記録装置の搭載など省令対応工事も行っています.
そして平成24年から令和4年にかけて,登場から20数年経過し老朽化してきた機器の若返りを図るため,1次から3次にわたり全20編成を対象に制御装置などの主要電気機器の更新が行われました.
その他,平成28年〜29年の2年間かけて,全20編成の弱電機器(信通機器)の更新が行われました.
| 年次 |
改造内容 |
| 平成5年〜6年 |
4→5両組成化
ATO搭載
ワンマン運転対応 |
| 平成20年〜23年 |
ホーム柵対応
省令対応 |
| 平成24年〜R4年 |
主要電気機器更新 |
| 平成28年・29年 |
弱電機器更新 |
|
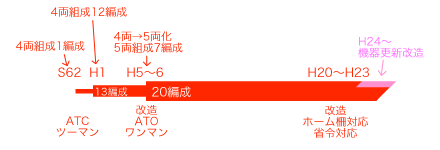 |
【令和11年度以降に車両更新(予定)】
令和11年には,一次車の導入から42年,二次車の導入から40年を超えることから,6000形の後継となる新型車両の製造が計画されています.
当初は早くて令和11年度(2029年度)導入が想定されていましたが,必要なR8予算措置がされておらず・・・,導入スケジュールは不透明です.
▼もどる |
