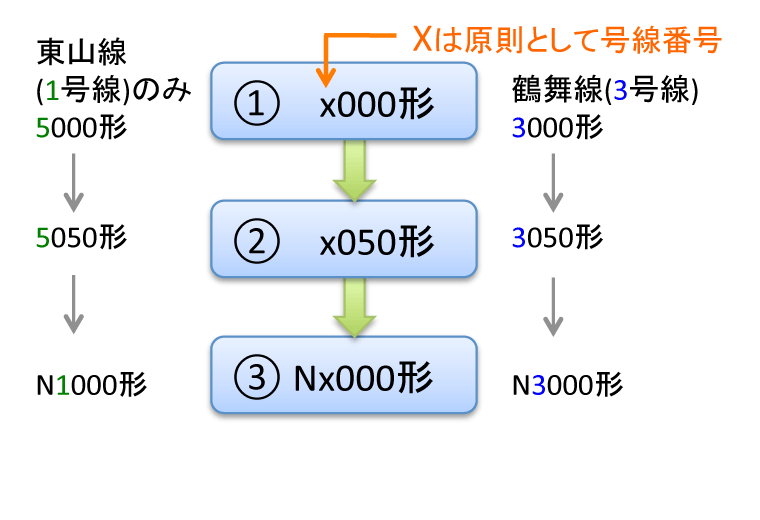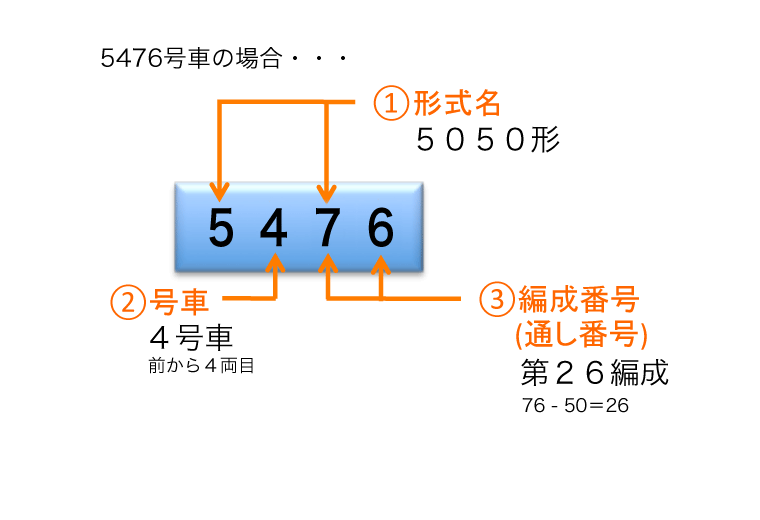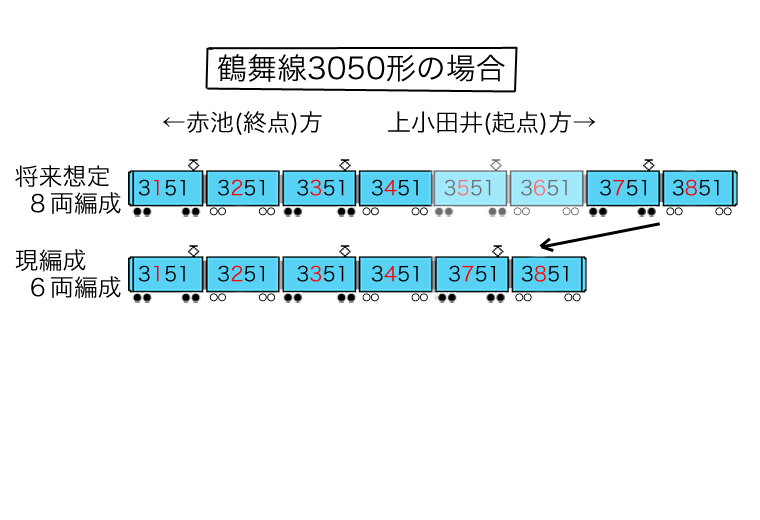|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地下鉄車両・編成を識別するために付与される各種番号のルールについて紹介します.
鉄道車両は,その種類や機能によって分類され,それぞれグループごとに車両形式が与えられます. JRや名鉄では○○系(けい)が使われますが,名古屋市営地下鉄では○○形(がた)が使われます.
名古屋市営地下鉄では,現在8形式が運用されています. 地下鉄開業当初の車両(黄電)は,東山線はx00形,名城線は1x00形という命名方法でした.
「x000形」の次に登場した形式は,+50番され「x050形」となりました. その次に登場した形式は,頭にNの文字を付した「Nx000形」となりました.頭文字Nには,次世代の名古屋の地下鉄を担う車両として「New」「Next」「Nagoya」の意味合いが込められています.
地下鉄車両は,路線によって6両もしくは5両,4両の固定編成を組み,運用されています. 名古屋市営地下鉄では,先頭車両の車両番号に,編成を示す呼称や記号を付けることで,編成記号としています. さらに省略して表記する場合は,地下鉄ではHenseiの「H」を使用しています.(※最下部注記) 参考までに,名鉄では他私鉄でも一般的なFormationの「F」を使用しています. 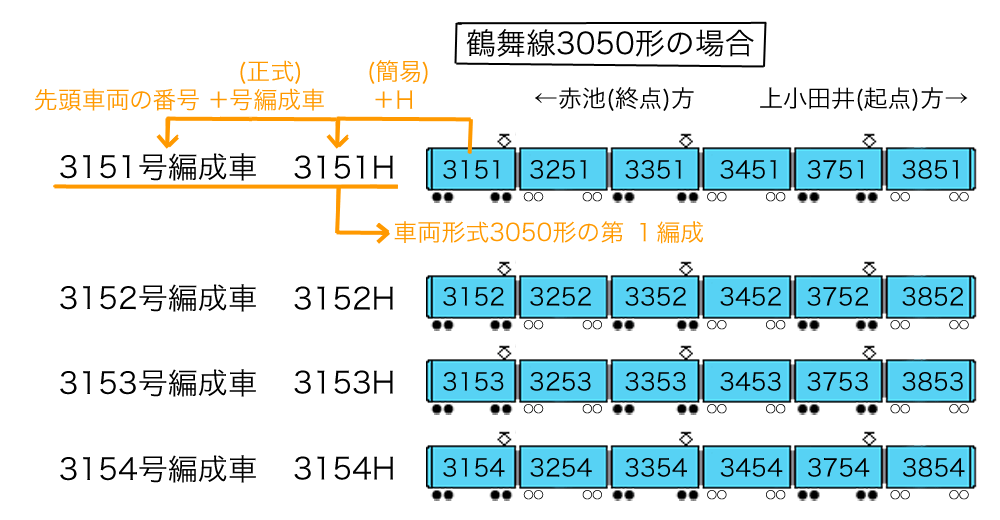 当ウェブサイトでは,地下鉄車は○○Hもしくは○○編成,名鉄車は○○Fもしくは○○編成と表記しています.
車両番号は,車両1両ごとに付与される固有の番号のことです(通称:車番). 黄電時代は,100形なら1xx,1200形なら12xxと,形式数字+下2桁が通し番号となっていました.
【表記例】
(※注記)編成記号の省略表記「○○○○H」について,公文書等を調べ上げ,過去に交通局内で同表記が使用されていたことを確認しています.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)まるはち交通センター製作委員会名古屋市交通局ファンサイト/名古屋市営地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||