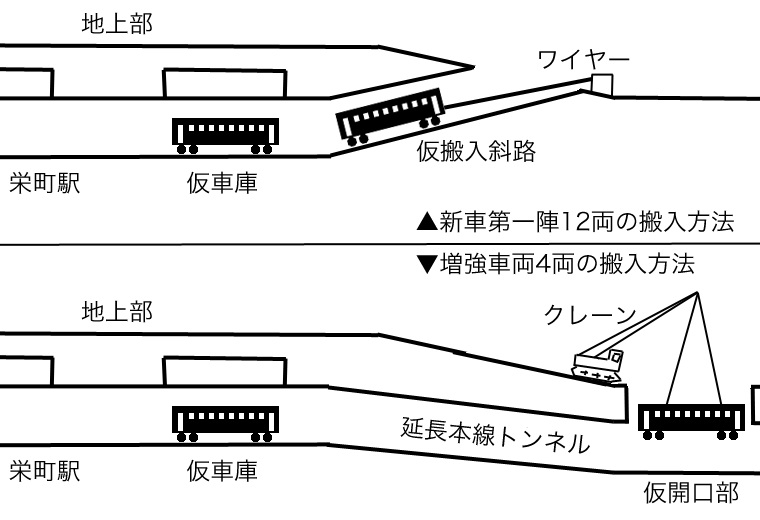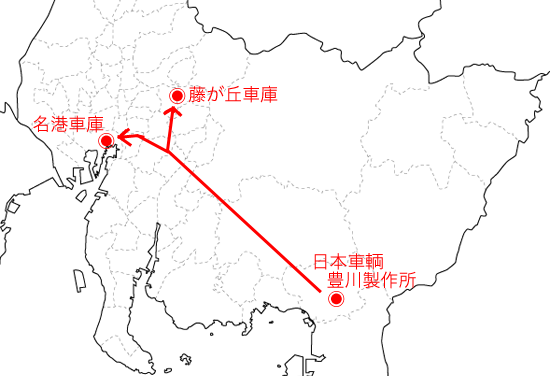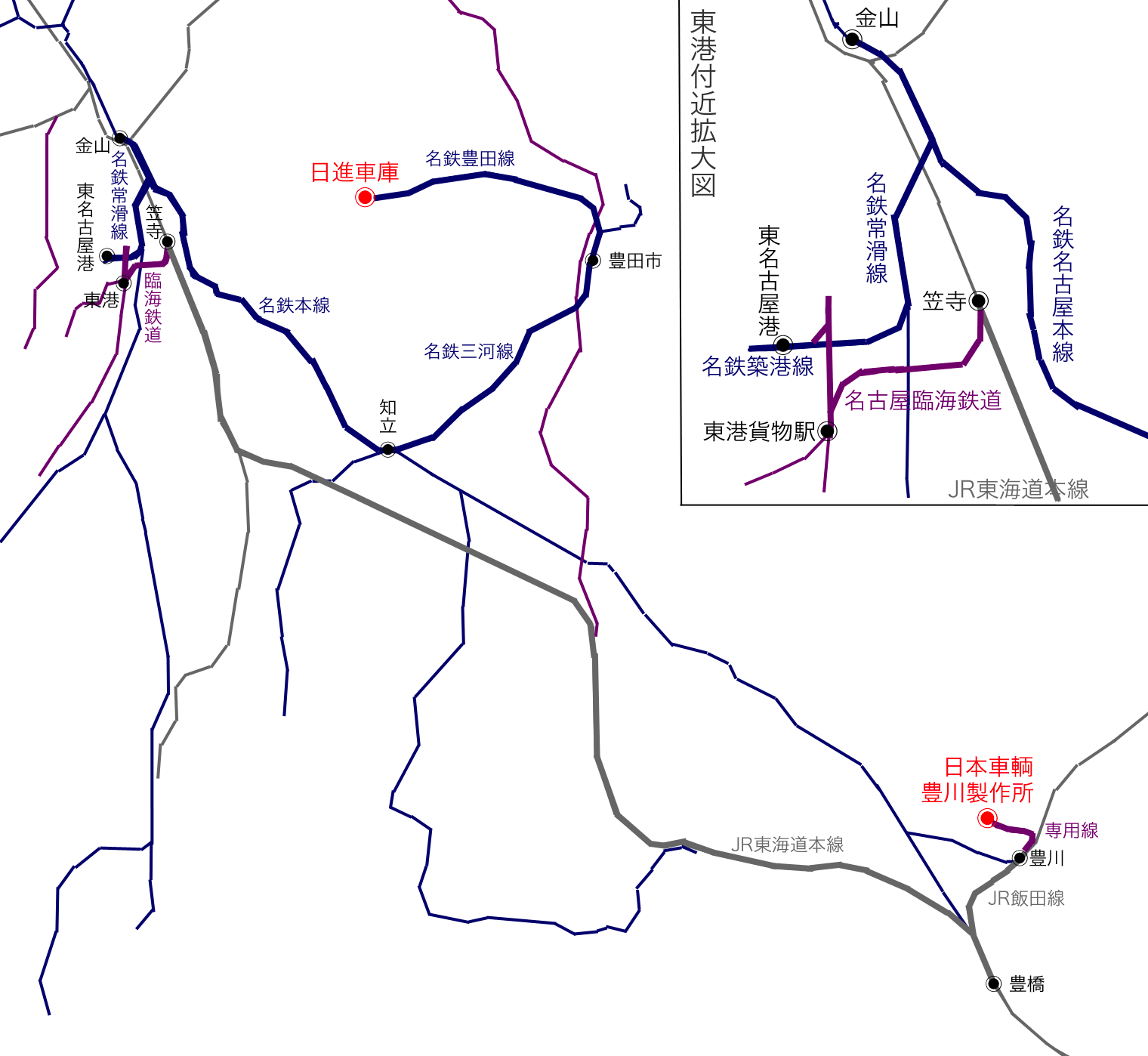|
地下鉄の新製車両の搬入/廃車車両の搬出方法を紹介します.
 地下鉄新製車両の搬入方法 地下鉄新製車両の搬入方法 |
 |
『地下鉄の電車はどこから入れたの?それを考えてると一晩中寝られないの。』――春日三球・照代
【昭和32年〜昭和35年】
地下鉄東山線(1号線)は,昭和32年に名古屋〜栄町(現在の栄駅)間で開業しました.
開業に先立ち,昭和32年9月に栄町仮車庫(地下)の東側に,勾配100‰の車両搬入路を設けて,新車第一陣12両の搬入が行われました.
この搬入路はその後の延伸工事にあたり本線トンネルとなったので,昭和34年1月の増強車両4両は延長トンネルに設けられた開口部(長さ20m,幅5m)(現在の栄公園付近)からクレーンを使って搬入されました.
【昭和35年〜昭和44年】
昭和35年に池下まで延伸されると同時に,地上部に池下車庫が設置されました.
以降,地上車庫での車両搬入が行われるようになりました.
 [参考]地下鉄車庫>池下車庫 [参考]地下鉄車庫>池下車庫
【昭和44年〜現在】
昭和44年に藤ヶ丘まで延伸されると同時に,地上部に藤ヶ丘車庫が設置されました.
それ以降から現在まで,地上車庫である藤ヶ丘車庫(現在の藤が丘車庫)にて車両搬入が行われています.
車両は夜間陸送により搬入されています.
【昭和40年〜?】
地下鉄名城線(2号線)は,昭和40年に市役所〜栄町(現在の栄駅)間で開業しました.
これと同時に地上車庫の名城車庫が開設され,ここから車両搬入が行われました.
 [参考]地下鉄車庫>名城工場 [参考]地下鉄車庫>名城工場
【?〜現在】
最終的に名城線車両の搬入作業は名港車庫にて行われるようになりましたが,いつ時点から名港車庫に移転したのかは,調査中です.
車両は夜間陸送により搬入されています.
【昭和52年】
地下鉄鶴舞線(3号線)は,昭和52年に伏見〜八事間で開業しました.
この区間には車庫や地上区間が無かったため,車両は荒畑〜御器所間の下り線トンネル上の道路に開口部(現在の昭和消防署付近)を設け,門型クレーンを使って搬入されました.
搬入された車両は最初に搬入したディーゼル機関車で八事の仮車庫まで牽引して整備しました.
 [参考]地下鉄車庫>本線臨時検車場 [参考]地下鉄車庫>本線臨時検車場
【昭和53年〜現在】
その後の赤池駅延伸開業に先立ち,昭和53年に日進車庫が完成しました.
以降,地上車庫での車両搬入が行われるようになりました.
鶴舞線車両はJRと同じ狭軌であり,名鉄線等を介してレールが繋がっているため,甲種鉄道輸送にて搬入されています.
 [参考]N3000形車両の搬入作業レポート [参考]N3000形車両の搬入作業レポート
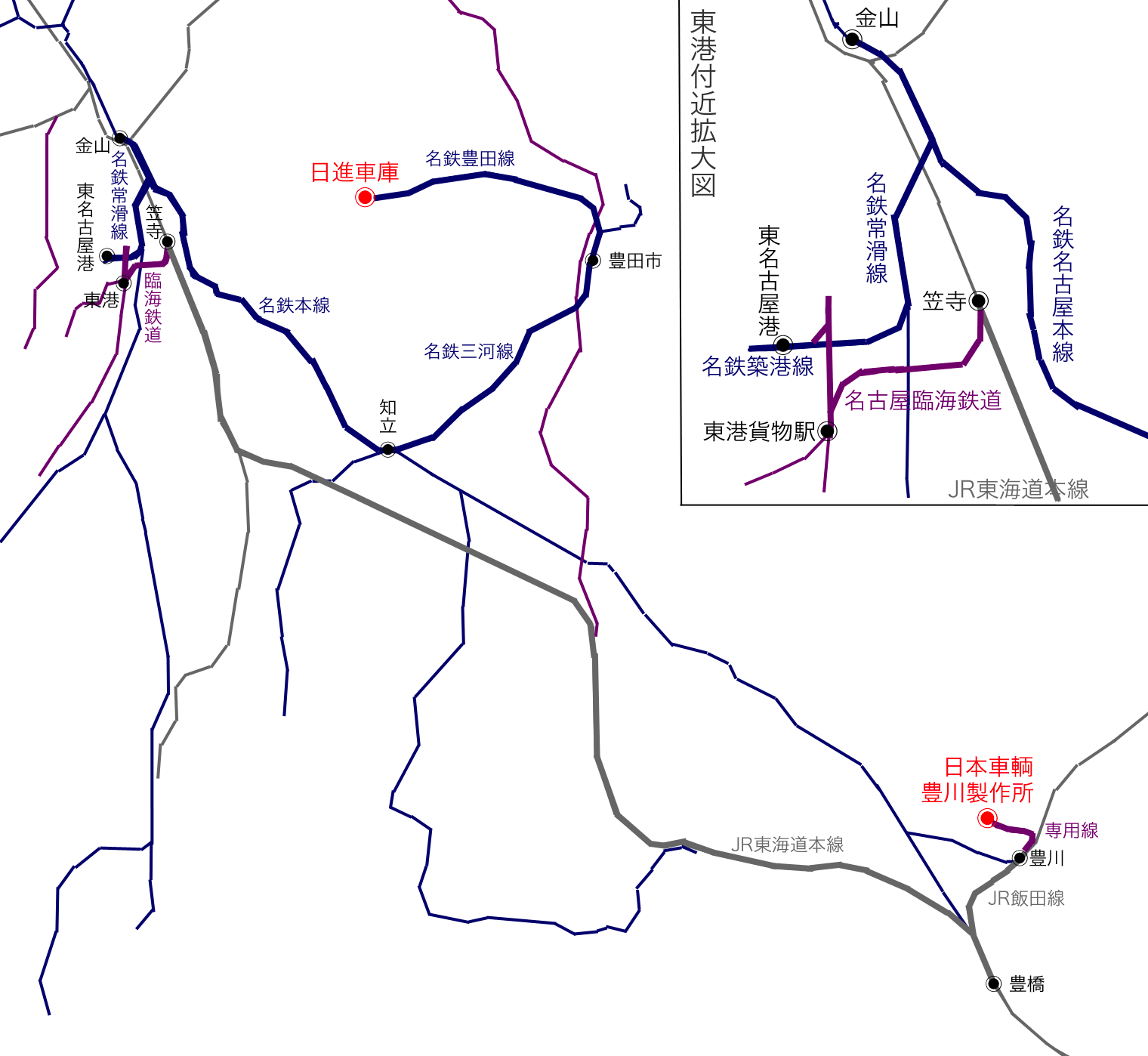 |

▲日本車両→日進工場のJR線甲種輸送 |
|
桜通線は丸の内駅で鶴舞線との間に連絡線があり,車両整備は鶴舞線を経由して日進車庫にて行なっています.
このため,車両搬入も地上車庫である日進車庫にて行われています.
鶴舞線車両と同じく,甲種鉄道輸送にて搬入されています.
 [参考]6050形車両の搬入作業レポート [参考]6050形車両の搬入作業レポート

▲日本車両→日進工場のJR線甲種輸送
(画像提供:ρさま) |
|
上飯田線の車両整備は名鉄に委託されており,普段は書類上の所属先である日進車庫に立ち寄ることはありません.
ただし,車両新製時は日進車庫に搬入され,ごく短い期間のみ日進車庫内で鶴舞線車両と桜通線車両,上飯田線車両が並ぶ光景を見ることができました.
 地下鉄廃車の搬出方法 地下鉄廃車の搬出方法 |
 |
地下鉄廃車車両の搬出方法について.
東山線の車両は、昭和57年6月の黄電100形廃車以降,黄電シリーズ全車と5000形全車が廃車されています.
このうち5000形の一部は,未だに藤が丘車庫内に留置されたままとなっていますが,その他車両は全て藤が丘車庫より搬出,もしくは解体&搬出されました.
 [参考]5000形車両の廃車搬出作業レポート [参考]5000形車両の廃車搬出作業レポート

▲車庫内解体パターン |

▲1両丸ごと搬出パターン |
名城線・名港線の車両は、平成2年6月の黄電1000形廃車以降,黄電シリーズ全車が廃車されています.
これら車両は全て名港車庫より搬出,もしくは解体&搬出されました.
鶴舞線の車両は、平成24年3月以降,3000形車両の廃車が進められています.
日進車庫内に留置されたままとなっている一部編成を除き,日進車庫より搬出,もしくは解体&搬出が行われています.
 [参考]3000形車両の廃車搬出作業レポート [参考]3000形車両の廃車搬出作業レポート

▲車庫内解体パターン |

▲1両丸ごと搬出パターン |
▼もどる |