 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地下鉄駅の深さ(高さ)を表す指標として,当ページでは次の数値を使用します. (1)地盤高(地面の高さ) ・・・地表面の海抜(絶対値)
海抜0m地帯の高畑駅を起点に,東部丘陵地帯の藤が丘駅まで,最も海抜差の大きい路線です. 一番最初に建設された路線であり,地上から比較的浅い位置に建設されているのが特徴です. 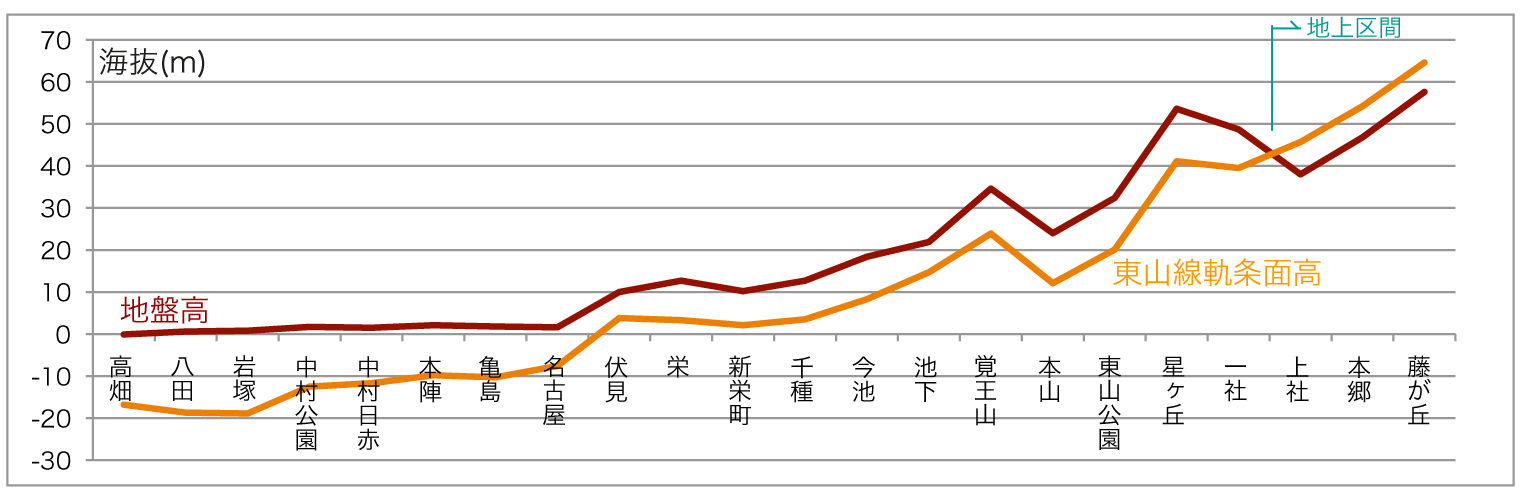
昭和時代に開業した西側区間(大曽根〜金山〜名古屋港・新瑞橋)は比較的平坦なエリアを走るのに対し,平成10年代に開業した東側区間は自由ヶ丘や八事日赤を頂点とした丘陵地帯を登り下りします. 名港線区間(金山〜名古屋港)は海が近く海抜も低いため,六番町駅以南5駅には高潮や津波に警戒して防潮扉が設置されています. 上飯田線は,上飯田駅の北側で河川を潜るため,平安通駅は地下4階にあるため,深い位置に建設されています. 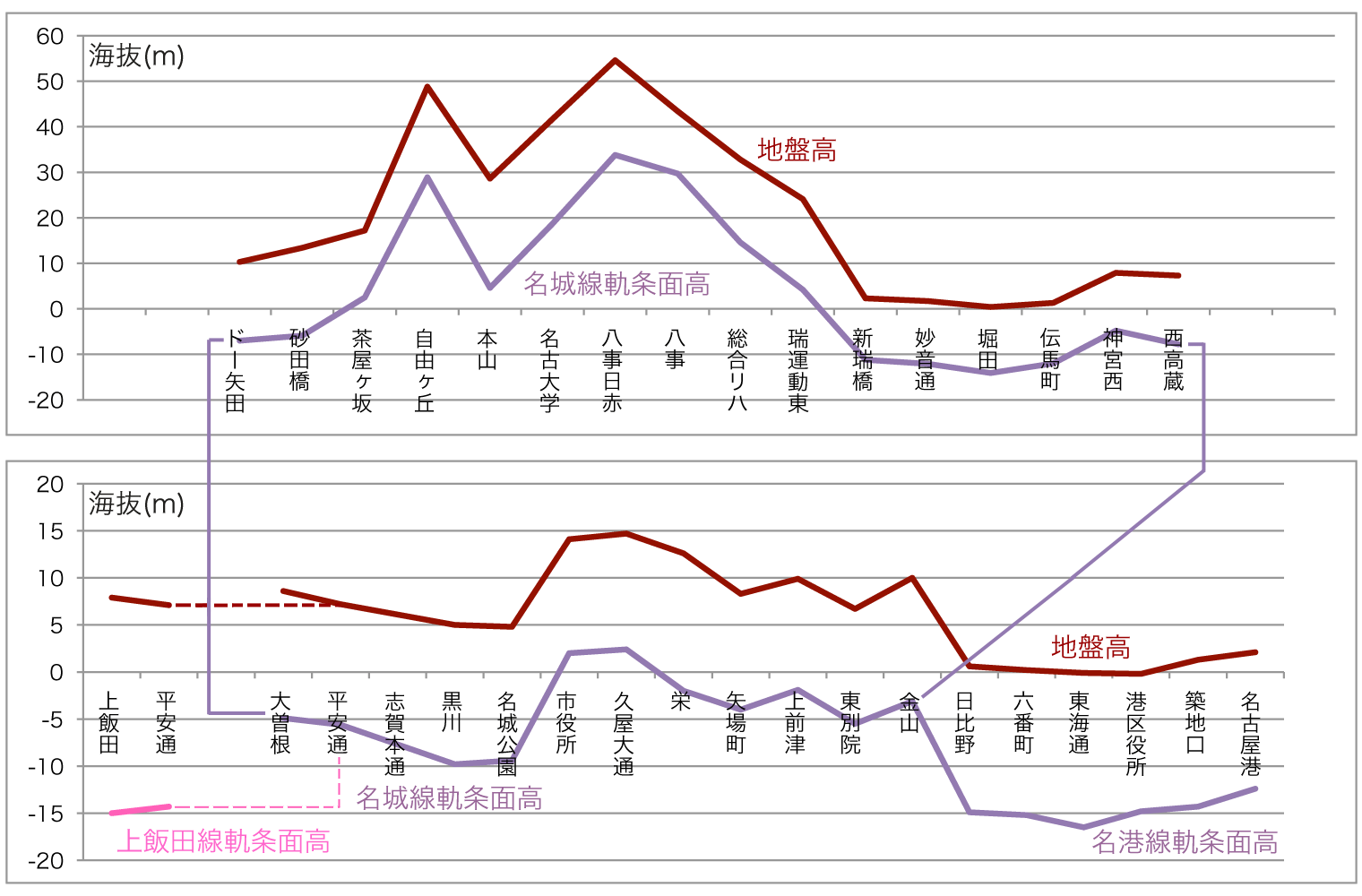
高架駅の上小田井駅を起点に,東部丘陵地帯の八事駅を超えて,郊外の赤池駅まで走る路線です. 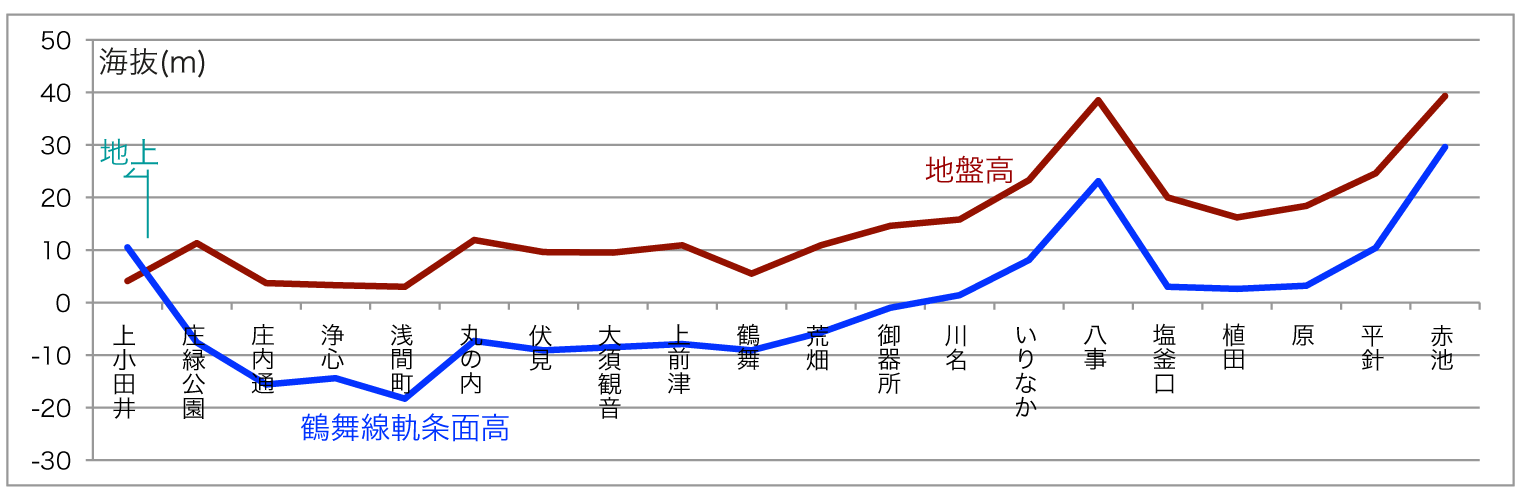
海抜の低い中村区役所駅を起点に,台地地帯(熱田台地,御器所台地,笠寺台地)(丸の内駅〜野並駅)を抜け,丘陵地帯の徳重駅を結ぶ路線です. 地下鉄他路線との交差や地下埋設物との競合を避け,地上から深い位置に建設されています. 一方で,地盤高や軌条面高の変化は比較的少ない路線で,軌条面高では最深の名古屋駅-19.1mから最高峰の神沢駅+21.6mまで,海抜差は40.7mです. 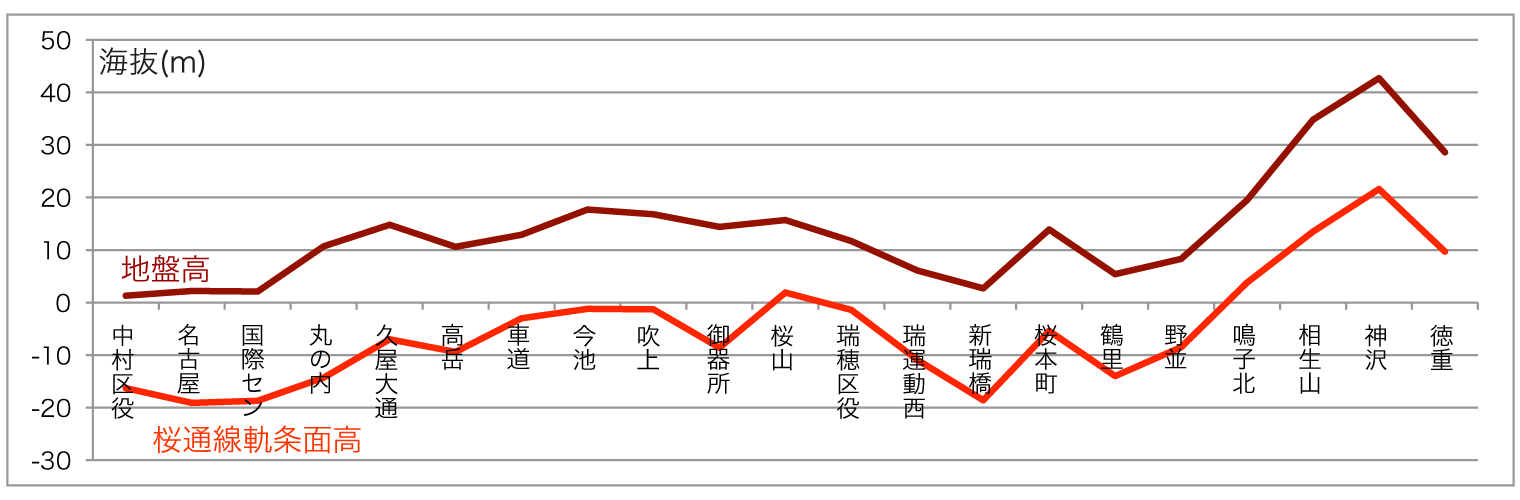
海抜(標高)に着目すると,一番高い駅は地盤高・軌条面高ともに東山線藤が丘駅(高架駅)です. 地下駅に限定すると,一番高い地盤高の駅は名城線八事日赤駅となりますが,地上面から軌条面までの深さは20.8mあるため,一番高い軌条面高の駅は東山線星ヶ丘駅(地盤高53.6m,深さ12.5m)となります. 一番低い地盤高の駅は,海に近い名港線港区役所駅です.一番低い軌条面高の駅は,JRや名鉄線,東山線の下に建設された桜通線名古屋駅となります.
(海抜に関わらず)地上からの深さが最も浅い地下駅は,東山線伏見駅です.ホームは地下1階で改札口よりも高い位置にあります. 地上からの深さが最も深い地下駅は,鶴舞線との交差駅である桜通線丸の内駅(-25.0m)です.
当ページの参考資料は次の通りです. 交通局資料では海抜表記としてKP(高速度鉄道基本水準面)が使用されていますが,建設時期によってTP(東京湾中等潮位)やNP(名古屋市工事用基本水準面)との差(読替え値)が異なるなど,やや複雑です. 海抜グラフは,各駅の地盤高と軌条面高のみを表示したものです.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) まるはち交通センター製作委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||